
病院や施設でも『転倒事故』って多いんですよね。

その通りです。最も多い事故ですね。そして、人の生活のお世話をする、わたしたち看護師や介護士にとっても、最も気をつけなければいけない事故とも言えます。

自分が当事者になると思うと、正直怖いです‥。

では、そうならないためにどうすればいいのか一緒に考えてみましょう!
『転倒事故』によって今まで良い関係を築いていた本人や家族から裁判所に訴えられるなんて想像したくはありませんよね。
2022年11月2日に、兵庫県立西宮病院における認知症患者さんの転倒事故についての裁判所の判決が出されました。
判決結果は病院側の過失(責任)が認められ、兵庫県に対して532万円の支払いを求めるものでした。
この判決は医療・介護業界に大きな波紋を与えたので、記憶に残っている方もいるかもしれません。
また『兵庫県立西宮病院の事例』と逆に‥『病院や施設の責任が認められなかった事例』というのもあります。
安全対策は入院患者さんや施設入居者さんの安全を守ることはもちろんですが、私たちの身を守ることもとても大切なことです。
この2つの事例を通して、どういった事に注意しなければいけないのかを、簡潔にわかりやすくお伝えしていきたいと思います!

楽天総合1位‥殿堂入りを果たした「BARTH 入浴剤」は高濃度の炭酸風呂で、と~っても疲れが取れますよ♪
身もこころも疲れている時は‥やっぱりお風呂♨ですね!
【看護師・介護士必見】転倒事故に関する2つの裁判事例を紹介

まず始めに、病院の責任が認められた「兵庫県立西宮病院における転倒事故」について紹介します。
(事例1)兵庫県立西宮病院での転倒事故の裁判事例
兵庫県立西宮病院において、2016年4月2日明け方に、看護師は認知症の男性患者(以下Aさん)をトイレに連れて行った後、別室にいた感染症患者(以下Bさん)のコールに呼ばれてAさんの傍を離れて対応した。
看護師が、Bさんの排便介助をしている最中に、Aさんはトイレで用を足し、そのまま一人で立ち上がって廊下を歩いてしまい、転倒して頭部を強く打ってしまった。Aさんは頭蓋骨骨折と外傷性くも膜下出血を起こして寝たきり状態となり、その2年後に心不全で亡くなった。
兵庫県(病院)側は、「別室にいたBさんが感染症患者(※何の感染症かは不明)だったため、ケアを優先させた」と主張をした。
裁判長は判決において、認知症の男性患者から目を離せば、勝手にトイレを出て転倒する可能性が高いことが十分に予見できたことを認めた。
また、別室にいたBさんがおむつに排便すれば問題がなかったことを指摘し、「(ケアを)優先しなければならなかったとは認められない」と指摘した。
判決としては、病院側の過失を認め、兵庫県に対して532万円の支払いを求めた。
後ほど、この判決に対するtwitter上の賛否両論についてはお伝えしますが、裁判官が『Bさんに対しておむつ内に排便させることを是(一般的に正しい)とした』のは、大きな波紋を読んでいます。
次に施設の責任が認められなかった事例について紹介します。
(事例2)有料老人ホームにおける転倒事故の裁判事例
平成26年、当時87歳であった脳血管性認知症のある高齢者(以下Cさん)は有料老人ホームに入所する以前から転倒歴が何度かあり、顔面の打撲や11針を縫う怪我をしたこともあった。
平成26年2月25日に有料老人ホームに入所した。
入所時の様子は軽度の失禁と帰宅願望が見られていたが、施設内を一人で歩行できており、会話による意思疎通も可能、さらにADLも自立してした。
またその後の月に1回のケアマネージャーによる確認では、CさんのADLは基本的に自立とされていた。
しかし、医師による居宅療養管理指導書施設内の記録では、「転倒に注意する」旨が記載されており、施設内では外出時は介助が必要な「準ねたきり状態」として管理されており、転倒にも要注意となっていた。
平成26年5月にリビングで食事を終えたCさんがトイレに行こうとして転倒し骨折した。その場には職員が2名いたが、他の入居者の対応をしており、すぐ傍にはいなかった。
裁判長による判決としては、「転倒に注意する」旨の記載はあるが、施設内では自立した歩行・生活を営めていることから、転倒事故を具体的に予見することは困難であったと認められた。
判決としては、事業者の責任が否定された。
【看護師・介護士必見】転倒事故で気を付けるべきこと

裁判事例から、わたしたち看護師・介護士が考えるべきポイントは2つあります。
1つは、『その人の転倒するリスクがあるかどうかの判断』です。
これは『予見可能性』と言われるものです。
わたしたちには、対象者が転倒するリスクがあるかどうかの判断をする義務(予見義務)があります。
その義務を果たした結果、転倒するリスクが実際にあるかどうか‥転倒事故が起きた場合に、その転倒事故が予見できたかどうかI(予見可能性)が大切になってきます。
そしてもう1つは、『その人の転倒リスクに応じた対策をとっているか』です。
これは『結果回避義務』と言われるものです。
つまり、転倒が予測されたのであれば、それに対してきちんと転倒予防策をとらなければならない義務があるということです。
また中には、その義務を十分に果たしていたけど、起きてしまう転倒事故というものもあります。
いわゆる『避けようのない不慮の事故』というもので、他の患者が転んだ拍子にぶつかってしまって転倒した場合などがそうです。
この場合は、転倒を回避する可能性(結果回避可能性)はないと判断され、結果回避義務も生じないということになります。
(事例1)(事例2)共に、予見義務を守り、『予見可能性』として、患者・療養者に転倒リスクがあることを病院・施設側がきちんと判断しています。
しかし、(事例2)では、客観的には転倒リスクがあるとは判断されないため、結果回避義務も生じません。
なので対策をしていなかったとしても仕方ないということになります。
つまり、最も大切な焦点は、客観的に『予見可能性』があるかどうかということになります。
またここで興味深いことは、(事例2)では、施設側が転倒リスクがあると予見していても、裁判所が客観的には「転倒リスクはなかった」と判断していることです。
病院や施設でも「普段はきちんと歩けているけど、高齢者だから少し注意した方がいいかな‥」くらいの判断(過大評価)で転倒リスクを考えて関わっていくこともよくあります。
しかし、それについては「転倒リスクがあると思ってたのに対策しなかった病院・施設が悪い!」とは言われません。
裁判では実際にリスクが高かったかどうかを再度審議することになります。
つまり、病院や施設において、対象者に対して転倒リスクがあるという判断(アセスメント)をすること自体は、過大評価をしても問題にならないということです。
逆に転倒リスクがある人に「転倒リスクがない」と判断する方が問題ですので、少しでもリスクを感じたのであれば、きちんと「転倒リスクがある」と記録にも書いていきましょう!
そして、もう1つ大切なことは、やはり必要十分な対策をきちんと行動に移すことです。
今回の(事例1)については、Aさんのトイレ歩行の介助を『行き』については、きちんと介助していますが、『帰り』については、できませんでした。
夜勤等で人数が少ないのであれば‥
できればしたくはないですが、『転倒するよりは‥』と考えて、『ポータブルトイレ』や『オムツの中にしてもらう』という対応をしていく必要があります。
(事例1)においても、看護師がベッド上での排泄を促したにも関わらず、転倒してしまったのであれば、『過失』にはならなかったと考えられます。

患者さんや療養者さんをトイレで排泄させてあげたいって気持ちはとても大切!

そうよね‥でも、その人の安全を守ること、また自分たちの身を守ることも同じように大切だね。

日勤帯で人がいるときはトイレへ、夜間で人手が足りないときは安全を考えてベッド上やポータブルトイレでの排泄をお願いするなど状況に合わせて対応していきたいですね。
『2022年11月2日兵庫県立西宮病院転倒事故の判決報道』に対するツイッター投稿を紹介

個人情報のこともあるため、アカウント名は載せておりません。

裁判長「認知症患者から目を離せば、勝手にトイレを出て転倒する可能性が高いことは十分予見できた」
これは全く現場のことがわかっていない発言!
現場の医療従事者で「頑張れば院内転倒ゼロにできる」と思ってる人は1人もいないのでは?
たとえ家族が24時間付き添ったとしても無理。
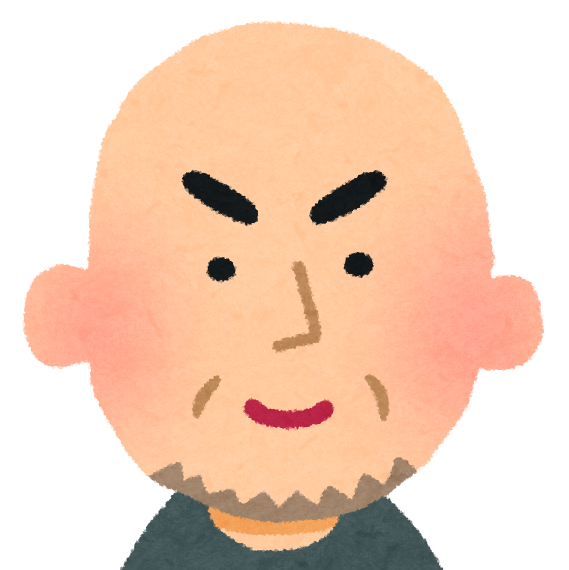
なんだこれは。仕事柄色々な医療機関で働いたり交流してますが、安全管理に最善を尽くしても転倒事故は拘束しない限り0には出来ない。
この裁判官の判決が悪しき前例となって似たような裁判が続出したらどうするんだ…
勿論病院側にも落ち度はあるだろうがこの判決はない。
看護師は「分身の術」や「どこでもドア」が使える超人ではありません。
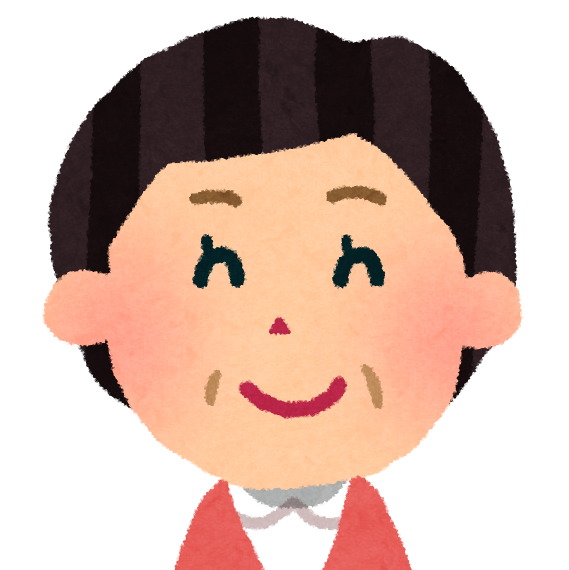
離床センサーがなれば全力で駆けつけているただの人間です。
転倒を防ぐのに「おむつ」を強制したり積極的に「抑制」をする、が答えでいいの?
この判決に「納得!」って言える看護師、この世に一人でもいるのかな‥?
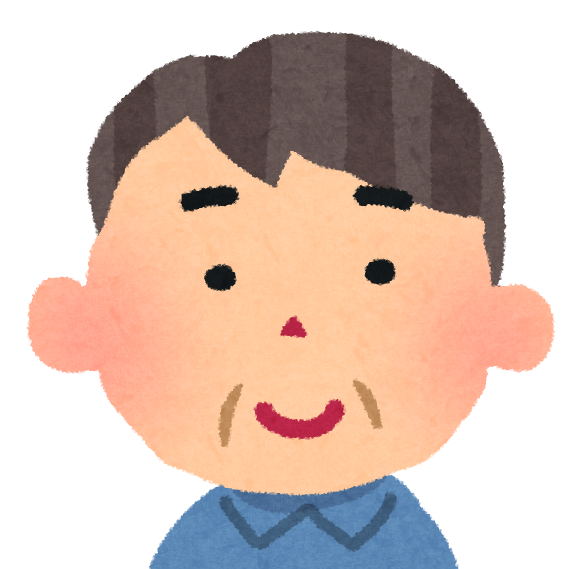
裁判所は、保険事故(交通事故、学校事故、労災事故、施設の高齢者転倒事故、火災、地震)の裁判では、有効な保険契約があることをもって、給付判決に仮執行宣言をつけない運用にしてくれないかな。

裁判所は、保険事故(交通事故、学校事故、労災事故、施設の高齢者転倒事故、火災、地震)の裁判では、有効な保険契約があることをもって、給付判決に仮執行宣言をつけない運用にしてくれないかな。
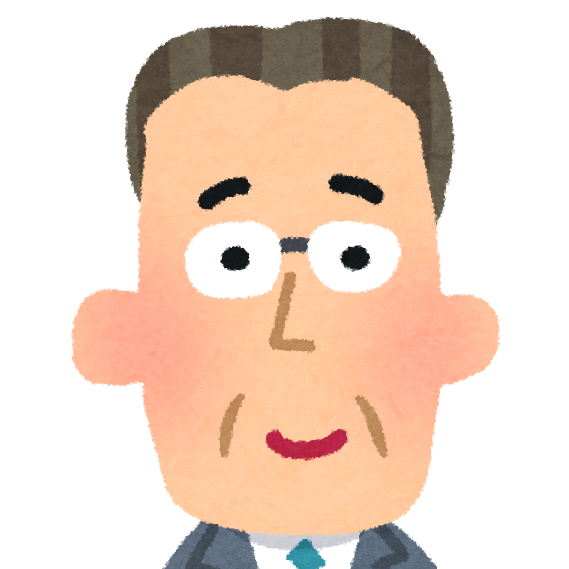
2016年に発生した転倒事故の損害賠償を求めた裁判の判決。判決に至るまでの裁判記事は見つからず情報不足だが厳しい判決。訴訟を起こした家族に批判が集中しないように。

今回のこの転倒事故はご家族さんにとって失ったものが大きすぎたのかも‥。そして裁判に踏み切ったのかな。ご家族や外からみた人にとってはこちらがどれだけ人数が少ないという事情を抱えていようが起こってしまった事故には変わりはないのよね。どっちの苦悩もわかるからな、難しいですね。
わたしも看護師であるため、この判決に対しては、詳細情報までは分からなかったものの、自分たちの身が守られない恐怖を感じました。
しかし、他方でもし自分の家族が転倒を起こしてしまったら‥命に関わる状態になったら‥と思うと納得できないかもしれない‥とも思います。
その際においても、病院や施設で十分な対策をしてもらっている中でそれでも起きてしまったら‥
家族の立場でも「仕方なかった」や、病院や施設に対しても感謝の気持ちも持てるのかもしれません。
看護師や介護士の立場だけでなく、転倒した当事者やそのご家族の立場、いろいろな立場に立って常に考えていきたいですね。
まとめ
病院や施設において、転倒事故で気を付けるべきことは、以下の2点です。
1.対象者に対して転倒リスクがあるかどうかの判断(アセスメント)をして記録に残す。
※少しのリスクでも『リスクがある』としておいて悪いことはない。
2.安全な対応策をしっかりとれるように状況に応じて臨機応変に判断・行動する。
また訴えられるのは、大抵が骨折などの重大な事故になってしまったケースであったり、本人や家族と良好な関係が築けていない場合です。
そのため、重大事故にならないようにするための工夫や、医療の基本ですが‥本人や家族との良好な関係形成も大切だと考えられます。
自分たちの身を守りながら、患者さんや療養者さんによいケアができるよう頑張っていきたいですね!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!

〈その他のオススメ記事〉
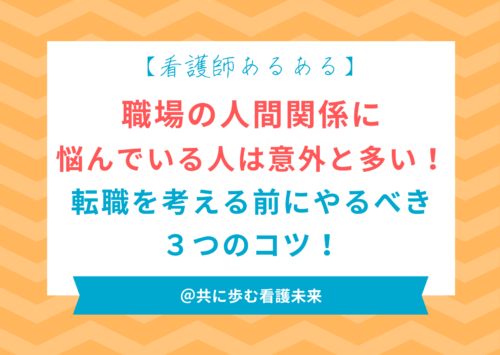
>>記事はこちら

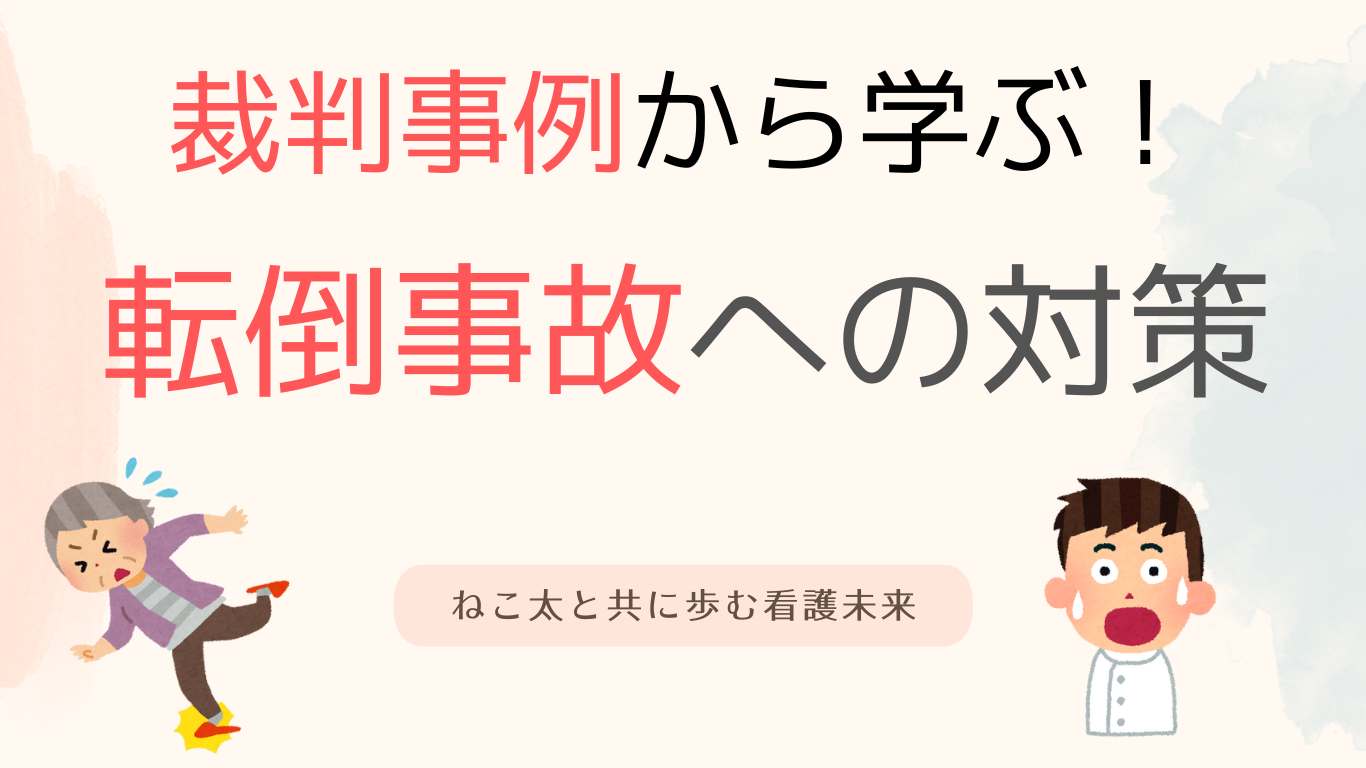



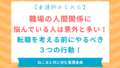
コメント